平安時代の位階と官職
平安時代の位階(官人の序列を示す等級)と官職についてまとめています。 皇族、後宮、摂政・関白、中央官制(二官八省)、 官位相当表、位階、地方官制、武士、僧侶、令外官、その他、番外編:位階を与えられた動物、四等官についてなどの説明があります。
本ページは、百人一首の歌人たちが就いていた官職の補助情報としてまとめたものです。専門家ではない個人作成のコンテンツであるため、学術的な厳密さを欠く箇所がある場合がございます。あらかじめご承知おきください。当時の官制を知ることで、歌の背後にある歴史や物語をより身近に感じていただければ幸いです。
皇族
| 称号 | 定義 |
| 上皇 | 譲位した天皇。太上天皇の略 |
| 准太上天皇 | 「太上天皇」に準じる地位。三条天皇の第一皇子・敦明親王が藤原道長から迫られて皇太子の地位を辞退する際、その見返りにとして「准太上天皇」という地位を与えられた。皇太子を辞退した見返りとしての特殊な例である。 |
| 治天 の君 |
院政を行う上皇。 複数の上皇が同時に存在する場合において政治の実権を握る上皇。 |
| 太皇太后 | 先々代の天皇の正妻。 |
| 皇太后 | 先代の天皇の正妻。 |
| 国母 | 天皇の生母である皇太后。「こくぼ」と読むこともある。 |
| 法皇 | 出家した上皇。太上法皇の略。 |
| 院 | 上皇・法皇・女院の尊称 ※もともとは上皇・法皇・女院の御所を指す言葉でした。 |
| 女院 | 皇后や皇太后(天皇の母や先帝の皇后)で上皇と同じ待遇を受ける者。 |
| 天皇 | 日本の君主。 |
| 親王 | 天皇による親王宣下(この子を親王とするという公的な宣言)を受けた天皇の兄弟、皇子、孫など。 |
| 内親王 | 天皇による親王宣下(この子を親王とするという公的な宣言)を受けた天皇の姉妹、皇女、孫など。 |
| 王 | 三世以下の嫡男系嫡出の子孫の男性。 |
| 女王 | 三世以下の嫡男系嫡出の子孫の女性。 |
| 若宮 | 幼い皇子。 |
| 東宮/春宮 | 皇太子。 |
| 儲けの君 | 皇太子。 |
| 中宮 | 天皇の正妻(皇后の別称)。 |
| 皇后 | 天皇の正妻(中宮の別称)。 |
| 后がね | 天皇の正妻候補。 |
| 斎宮 | 伊勢神宮に奉仕した皇女。 |
| 斎院 | 賀茂神社(上賀茂神社、下賀茂神社)に奉仕した皇女。 |
後宮
| 呼称 | 定義 |
| 女御 |
中宮に次ぐ地位 (中宮・皇后候補になり得る) 御殿の名称に女御を付けて区別した。(例:弘徽殿女御) 清涼殿(天皇の日常の御殿)の近くの御殿を与えられるほど、天皇の寵愛が深く、実家の政治力も強い。 |
| 更衣 | 女御に次ぐ地位 (中宮・皇后候補になり得ない) 清涼殿(天皇の日常の御殿)から遠い御殿(桐壺など)を割り振られることが多い。 |
| 御息所 | 女御、更衣または、それ以外の身分で天皇の寵愛を受けた女性の総称。 |
| 女房 | 宮中や貴族の屋敷で高貴な人の身の回りの世話や教育係を務める女性。 |
| 召人 | 主人と男女の関係のある女房。 |
| 上の女房 | 天皇に仕える女房。内侍司に所属する女性。 |
| 宮の女房 | 中宮(正妃)に仕える女房。后やその庇護者から私的に雇われる女性。 上臈(三位以上の上級貴族出身) > 中臈 (四位・五位の中級貴族出身) > 下臈と階層が分かれる。 |
| 女房三役 | 宣旨・御匣殿(御匣殿の別当)・尚侍は、女房の中で重職で、女房三役と呼ばれた。 |
| 宣旨 | 女房集団の筆頭。尚侍に相当する最高職で、第一秘書のような役割をしたり、女房集団を統括した。「宣旨女房」とも呼ばれた。 |
| 御匣殿 | 「御匣殿」は、後宮で衣服や裁縫を担当する女官たちが働いていた場所のことだが、その場所を取り仕切っていた女性は、「御匣殿の別当」と呼ばれ、略して「御匣殿」とも称された。 |
| 尚侍 | 尚侍は、本来は天皇の側近として秘書官的な役割と強い政治的影響力を持っていましたが、蔵人頭の設置によりその政治力は失われ、後宮の職務に専念するようになった。尚侍は、内侍司の長官。 |
| 命婦 | 五位以上の女官と、五位以上の官人の妻。 |
| 女蔵人 | 宮中に奉仕した下級の女房。内侍・命婦の下で、雑用を務めた。 |
| 得選 | 御厨子所の女官で食膳および雑事に従事した女房。采女 から選ばれたことが「得選」の名前の由来になった。 |
| 采女 | 天皇・皇后の側近に仕え、食前などの日常の雑事に従った者。 |
| 女嬬 | 内侍司に所属し、雑用を担当した13歳~30歳までの女性。 |
女房の「房」は部屋のことで、女房は自分の部屋(屏風や几帳で区切った空間)を与えられ、住み込みで働いていた。
後宮の場所
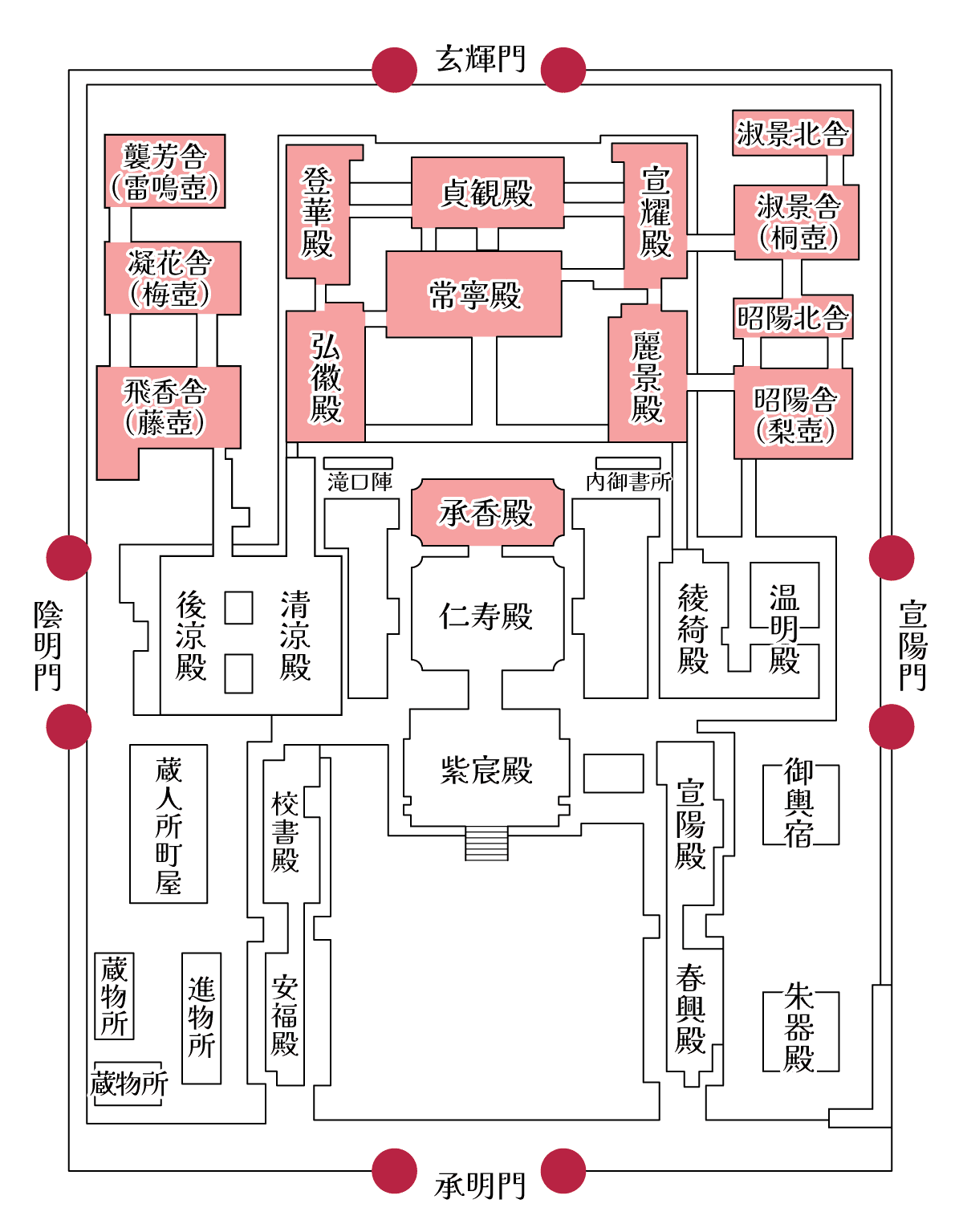
上図はクリックすると拡大表示されます。
呼ばれることもあります。
登華殿・弘徽殿・貞観殿 ・常寧殿・
承香殿・
麗景殿・宣耀殿のことです。
襲芳舎(雷鳴壺)・凝花舎 (梅壺)・
飛香舎(藤壺)・淑景舎(桐壺)・
昭陽舎(梨壺)のことです。
後宮十二司
| 名称 | 役割 |
| 内侍司 | 天皇の秘書・伝達。天皇への取次や儀式の進行を司る。 |
| 蔵司 | 神璽(天皇の印)関契(関所の通行証)、御装束 の管理を司る。 |
| 書司 | 書籍および紙・墨・筆・机などの文房具の管理を司る。 |
| 薬司 | 医薬の管理および天皇への服薬の補助を司る。 |
| 兵司 | 兵器の管理を司る。 |
| 闈司 | 宮中の御門の鍵管理を司る。 |
| 殿司 | 輿繖(乗物の輿とその上に差し掛ける長い柄のついた傘)、膏沐(入浴・整髪用品)、清掃、火燭 などの管理を司る。 |
| 掃司 | 施設の維持管理、屏風などの調度品の設営、清掃などを司る。 |
| 水司 | 飲料水や、軽食である粥、氷などなどを司る。 |
| 膳司 | 天皇の食膳の調理や管理、毒見などを司る。 |
| 酒司 | 酒の醸造、酒器の管理などを司る。 |
| 縫司 | 衣服の裁縫や組紐を編むことなどを司る。 |
内侍司
内侍司は令によって定められた後宮十二司の一つで、天皇に近侍し、奏上や伝達を担う役所です。当初、後宮には12の役所がありましたが、平安中期以降、他の11司の実務は次第に衰退し形骸化していきました。これにより、内侍司が後宮における女官組織の実質的な中心となりました。
春宮坊
天皇の家政を「宮内省」が担うのに対し、皇太子の家政を専門に担う独立した役所が春宮坊です。皇太子は「次期天皇」という極めて特別な立場にありますが、即位前であるため、現役の行政組織である「二官八省」の枠組みには含まれません。そのため、太政官の指揮系統に属さない独立した組織として、太政官と並び立つような形で設置されました。
| 名称 | 役割 |
| 主膳監 | 皇太子の食事の調理や毒見を担当。 |
| 主蔵監 | 皇太子の財産、宝物、衣類などの出納・管理を司る。 |
| 舎人監 | 皇太子の身辺警護や雑務を担う舎人の管理を司る。 |
| 主馬署 | 皇太子が乗る馬や馬具の管理を司る。 |
| 主殿署 | 皇太子の住まいの清掃、照明、お風呂の管理を司る。 |
| 主書署 | 皇太子の教育に使う書籍、紙、筆墨の管理を司る。 |
| 主兵署 | 皇太子の護衛に使う武器や武具の管理を司る。 |
| 主工署 | 皇太子の住まいの修理や家具・道具の制作を司る。 |
| 主漿署 | 皇太子の飲む飲料(お粥、酒、酢、水など)の管理を司る。 |
摂政・関白など
摂政や関白は律令の令制に規定がなく新設された令外官と呼ばれる官職です。藤原基経の子孫である藤原北家嫡流によって世襲され、絶大な権力を誇りました。
| 称号 | 定義 |
| 摂政 | 幼少の天皇に代わって政務を執る。 |
| 関白 | 成年後の天皇を補佐して(ほぼ実権を握って)政務を執る。 |
| 内覧 | 関白に準じる地位。天皇に奏上する文書、天皇が裁可する文書を事前に目を通すなどして天皇を補佐する。 |
| 阿衡 |
「摂政」、「関白」の異称。 887年、宇多天皇は藤原基経に補弼を要請するため、橘広相に「阿衡の任をもって卿(基経)の任とせよ」という詔を作成させました。しかし、基経は「阿衡」は実際の職掌がない名誉職であるとして職務を放棄し、政務を停滞させる「阿衡の紛議」を起こしました。この政治紛争は菅原道真によって解決されました。 |
| 太閤 | 摂政または関白の職を退いて後、嫡男に摂関の職を譲った者への敬称。 |
| ミウチ人 | 天皇の外戚(母方の祖父や叔父)になることで、天皇との血縁関係を持った摂関家。周囲の貴族から重んじられ、権力基盤が強固になった。 |
| ヨソ人 | 天皇の外戚関係にない摂関家。周囲の貴族から軽んじられ、権力基盤が弱かった。 |
中央官制
平安時代の中央官制は、国家の祭祀を担当する神祇官と国政を統括する太政官 があり、太政官の下に八つの省が置かれる「二官八省」と呼ばれる体制をとっていました。

神祇官
神祇官は、国家の祭祀を司ったり、全国の神官を管理する役所でした。二官八省の図では、神祇官と太政官は天皇の下に「並列」に描かれていますが、実際は太政官の指揮を仰ぐ立場でした。
摂政・関白・内覧
摂関政治の確立: 天皇の直下に摂政・関白が位置し、天皇への奏上を事前に確認する内覧を兼ねることで、藤原氏は国政の実権を握りました。>
太政官
太政官は、現代の「三権分立」とは異なり、行政・立法・司法の全権限を束ねて国家運営を司る中枢でした。
大臣・大納言 ・中納言・参議 たちが陣定と呼ばれる政策会議を開き、国家の方針を合議し、決定しました。
少納言は、かつては天皇の側近でしたが、嵯峨天皇が810年に「蔵人所」という新しい令外官を設置すると、実権を失い、天皇の印鑑や駅鈴を管理する儀礼的な事務に職権が抑えられました。
左右の弁官局が司令塔となり、決定事項を具体的な命令として八省に具体的な命令を下しました。
令外官の台頭: 律令に規定のない新設の官職である内大臣 ・中納言・参議 (宰相)、さらに准大臣(儀同三司)などが政治の中枢に加わりました。
豆知識
- 百人一首に登場する儀同三司母(54番)は息子の藤原伊周が儀同三司を名乗っていたことに由来します。
下表は太政官の四等官制です。
| 階級 | 官職 |
| 長官 一等官 |
太政大臣 > 左大臣 > 右大臣 > 内大臣 |
| 次官 二等官 |
大納言 > 中納言 > 参議 (宰相 ) |
| 判官 三等官 |
少納言 ・ 左右弁官(大>中>少) |
| 主典 四等官 |
外記(大・少) ・ 左右史(大・少) |
太政大臣は「則闕の官」とも呼ばれ、適任者がいない場合は欠員になりました。
特にこれといった仕事はなく、欠員状態が常でした。
権大納言のように頭に「権」が付くのは、定員を超えて任官された者です。
豆知識
かつてテレビで大人気だった時代劇ドラマ「水戸黄門」の名は、主人公である徳川 光圀が水戸藩主であることと官職である「権中納言 」を、唐名で「黄門」と呼ぶことに由来しています。ちなみに「権」は中納言の本来の定員(3名)を超えて任命されたことを示します。
太政官と諸官司の構造

太政官は、すべての「省」を束ねる最高機関で、現代の内閣・国会・最高裁判所の機能を併せ持ったような存在でした。
「省」は、現代の各省庁に相当します。
その配下にある「職」と「寮 」を比べると、「職」の方が組織規模が大きく、格上とされていました。平安時代では、皇后を支える「中宮職 」や、都の行政・司法を担う「京職」などが置かれ、特に重要視されました。
一方、「司 」は職や寮よりもさらに限定された専門実務を担う最小単位の組織でした。司の多くは寮の配下に置かれましたが、天皇に近い部署は、規模が小さくても「司」として独立し、寮を介さず省から直接指揮を受けました。
中務省
この図は、中務寮の傘下組織を表したものです。中務省の「中」は禁中 を表し、務は「政務」を表しています。中務省は天皇のすぐ側にあり、国の重要なルールや人事を司る機関で、太政官の配下にある八省の中でもっとも重要な存在でした。
| 名称 | 役割 |
| 太皇太后宮職 | 天皇の祖母に仕え、その生活や事務全般を支える。 |
| 皇太后宮職 | 皇太后(先代の皇后、天皇の母など)仕え、その生活や事務全般を支える。 |
| 皇后宮職 | 皇后(天皇の正妻)に仕え、その生活や事務全般を支える。 |
| 中宮職 | 中宮(天皇の正妻)に仕え、その生活や事務全般を支える。 |
| 大舎人寮 | 宮中警護・雑務の担当。天皇の身辺で警護や儀式の行列に加わる。 |
| 図書寮 | 書籍・仏像の管理。図書の収集・保管や、写経、紙・墨の製作も担う。 |
| 内蔵寮 | 天皇の私財管理。献上物や御料物の収蔵・出納を司る「天皇の財布」。 |
| 縫殿寮 | 衣服・裁縫の担当。天皇の衣服の製作や、女官の人事管理も行う。 |
| 陰陽寮 | 天文・暦・占いの担当。吉凶の判断や時刻の測定、暦の作成を行う。 |
| 内匠寮 | 工芸・装飾の担当。宮中の器物製作や儀式の設営、建物の装飾を担う。 |
豆知識
- かつて「皇后」と「中宮」は天皇の后(正妻)を指す同義語でしたが、藤原道長の政治的戦略によって二つに切り離されました。
- 道長は娘の彰子を一条天皇の后にするため、すでに后だった定子を「皇后」とし、彰子を「中宮」としました。これにより「皇后宮職」と「中宮職」という2つの組織が誕生することに。平安時代中期に宮廷内に2つの文化サロンができたのはこうした背景があったのです。
- 百人一首に登場する清少納言(62番)は定子に仕えていたため「皇后宮職」に所属し、同じく百人一首に登場する赤染衛門(59番)、紫式部(57番)、和泉式部(56番)、伊勢大輔(61番)などは彰子に仕えていたため「中宮職」に所属しました。
- 陰陽寮において定員6名・従七位上の専門技官に過ぎなかった陰陽師の立場ながら、安倍晴明は類まれな占術の才能で摂関家の絶大な信頼を勝ち取り、最終的には四等官の枠組みを超えて長官である陰陽頭(従五位下)をも凌ぐ従四位下へと昇進するという、官僚制の常識を覆す異例の出世を遂げました。
式部省
この図は、式部省の傘下組織を表したものです。式部省は、大学寮の管理や文官の人事考課や叙位を行っていました。また、散位寮(位階だけあって、職のない文武官を管理する機関)も管理していました。
| 名称 | 役割 |
| 大学寮 | 大学寮は、国立の大学で官僚の養成を担いました。 |
| 散位寮 | 散位寮は、位階を持ちながら具体的な職務に就いていない者の名簿を作成・管理する機関でした。他の役所からの要請に応じて人員を派遣したほか、その勤怠管理も担っていました。これは唐にはない日本独自の組織でした。896年の行政整理により式部省へ吸収・統合され、寮ではなくなり、式部省という大きな組織の中の一部署として組み込まれました。 |
大学寮の学科
大学寮では紀伝道(中国史・漢文学)、明経道(儒学)、明法道(法学)、算道(算術)の4つの専門学科がありました。平安時代においては紀伝道が主流になりました。
紀伝道の階級
| 階級 | 定義 |
| 文章博士 | 大学寮の紀伝道(漢詩文中国の歴史を学ぶ学科)の教官 |
| 文章得業生 | 文章生から優秀者2名が選出される特待生 |
| 文章生 | 擬文章生からさらなる試験に及第した学生 |
| 擬文章生 | 大学寮と呼ばれる律令制のもとで作られた式部省が直轄する官僚育成機関で寮試と呼ばれる試験に及第した学生 |
明経道の階級
| 階級 | 定義 |
| 明経博士 | 大学寮の経書(儒教でとくに重視される文献)の教官1名。 中原氏と清原氏が代々、大外記となって任じられた。 |
| 助教 | 明経博士を支え教官2名 |
| 直講 | 明経博士と助教を支える教官2名 |
| 明経得業生 | 明経生から2名選出される特待生 |
| 明経生 | 明経道を学ぶ学生 |
明法道の階級
| 階級 | 定義 |
| 明法博士 | 大学寮の法学の教官2名。 |
| 明法特業生 | 明法生から2名選出される特待生 |
| 明法生 | 法学を学ぶ学生 |
算道の階級
| 階級 | 定義 |
| 算博士 | 大学寮の算術の教官2名 |
| 算特業生 | 算生から2名選出される特待生 |
| 算生 | 算術を学ぶ学生 |
音道
音道は独立した学科ではなく、大学寮(特に紀伝道と明経道)で学ぶ学生の基礎的なスキルを身につける学科でした。
| 階級 | 定義 |
| 音博士 | 大学寮で中国語の発音を教える教官2名 |
| 音生 | 大学寮で中国語の発音を学ぶ学生 |
書道
書道は独立した学科ではなく、大学寮(特に紀伝道と明経道)で学ぶ学生の基礎的なスキルを身につける学科でした。
| 階級 | 定義 |
| 書博士 | 大学寮で書道を教える教官2名 |
| 音生 | 大学寮で書道を学ぶ学生 |
治部省
この図は、治部省の傘下組織を表したものです。治部省は、宮中の儀式や外交事務、僧尼の管理を幅広く担っていました。傘下には、宮廷音楽や舞踊を司る雅楽寮、僧尼の管理や外交使節の接待を担う玄蕃寮、そして天皇・皇族の墓所を管理する諸陵寮(もとは諸陵司)などが置かれていました。
| 名称 | 役割 |
| 雅楽寮 | 雅楽寮は、宮廷における音楽、舞踊、およびそれに関わる教育を行っていました。 |
| 玄蕃寮 | 玄蕃寮は、僧尼の管理と外交使節の接待を行っていました。平安時代には鴻臚館と呼ばれる海外交易の施設が京都、大阪、福岡に置かれており、新羅や渤海からの使節をもてなしました。 |
| 諸陵寮 | 諸陵寮は、皇族の陵墓の管理、皇族葬儀の儀礼などを行っていました。もともとは、諸陵司 という小規模な組織でしたが、嵯峨天皇の御代に皇室の権威を象徴する儀礼や陵墓管理をより格式高いものにするため、「寮」へと昇格したと言われています。 |
豆知識
- 百人一首に登場する僧正遍昭(12番)が五節の舞姫の歌を詠んでいますが、その五節の舞の指導や伴奏も、雅楽寮が中心となって行いました。
民部省
この図は、民部省の傘下組織を表したものです。民部省は、国の基盤となる「財政」と「戸籍」を一手に司っていました。現代で例えるなら、財務省と総務省を合わせたような強大な権限を持つ省でした。よくある誤解として、大蔵省が税の徴収を行っていたと思われがちですが、戸籍を管理し税を取り立てるのは民部省の仕事です。対する大蔵省は、その名の通り「蔵」の番人でした。民部省が全国から集めてきた物品や宝物を大切に保管し、その出納を管理することが主務でした。
| 名称 | 役割 |
| 主計寮 | 主計寮は、「国家予算の編成」と「税収の計算」を一手に担う実務機関でした。主に都に直接運ばれる地域の特産品である「調」がどれだけ入ってきて、どのように使うか(宮中の儀式、役人の給与、各省への予算配分)を決めていました。 |
| 主税寮 | 主税寮は、地方に備蓄される稲である「租」の管理と、地方財政の監査を担っていました。律令時代の行政単位には、国と郡があり、国衙や郡衙には「正倉」と呼ばれる金庫がありました。奈良の東大寺にある「正倉院」は、お寺の倉庫群で、そのうち唯一現代まで残った一棟として世界的に知られています。主税寮が管理していたものではありませんが、建物の造りは同じだったと考えられます。 |
兵部省
この図は、兵部省の傘下組織を表したものです。兵部省は、軍事と国防の総司令部で、現代の防衛省にあたります。その業務は幅広く、南九州の大隅半島、薩摩半島付近に住んでいた武勇に優れた「隼人」の人々を管理し、都の警護や儀式の演舞(隼人舞)に従事させました。また、外国からの襲撃に備え、昼は煙、夜は火を上げてリレー形式で情報を伝える超高速通信ネットワーク「烽」の維持管理も担当していました。さらに、全国各地に「牧」と呼ばれる国営の軍馬育成牧場を設置し、軍馬や駅馬を育成していました。
| 名称 | 役割 |
| 隼人司 | 隼人司は、南九州の大隅半島、薩摩半島付近に住んでいた武勇に優れた「隼人」の人々を管理・統括しました。 |
豆知識
- 京都府京田辺市には「大住」という地名がありますが、この地名は、隼人がこの地に移住してきたことに由来しています。現在でも、京田辺市の月読神社では、毎年10月に大住隼人舞が奉納されており、兵部省が守り伝えた古代の息吹を感じることができます。
刑部省
この図は、刑部省の傘下組織を表したものです。刑部省は、司法の最高機関として、法律(律令)に照らして罪の重さを決める「裁判」と、判決に基づく「刑の執行」を主導しました。科される刑罰は、重さに応じて次の5種類に分かれています。
- 笞
- 細い竹の鞭で、背中や臀部を叩く刑。回数は10回〜50回までの5段階。
- 杖
- 笞よりも太い杖で背中や臀部を叩く刑。回数は60回〜100回までの5段階。
- 徒
- 一定期間(1年〜3年)、役所などで強制労働をさせられる刑。
- 流
- 故郷から遠く離れた土地へ強制的に移住させられます。距離によって「近流・中流・遠流」の3段階。
- 死
- 最高刑である「死刑」です。絞首刑(絞)と斬首刑(斬)の2種類。
| 名称 | 役割 |
| 囚獄司 | 刑部省の配下にある囚獄司は、現代の刑務所にあたる獄舎の管理を専門とする役所でした。 |
刑部省は、法律に則って罪状を照らし合わせ、審理しましたが、重大な刑罰や、法律の解釈が分かれる複雑な訴訟については、刑部省の審判結果をふまえ、太政官が最終的な裁定を下しました。
平安時代中期以降、治安維持の専門職である検非違使 が台頭します。検非違使が犯人の逮捕から裁判、さらには獄舎の管理までを一括して行うようになると、刑部省と囚獄司は実務の場を失い、組織として形骸化していきました。
大蔵省
大蔵省は、民部省が諸国から集めてきた調(布や各地の産物などの品々)や金銀、銭貨を厳重に預かり、品々の良し悪しを見極め、一分の狂いもなく蔵に納める「国家の蔵」の役割を担いました。
| 名称 | 役割 |
| 織部司 | 大蔵省の配下にある織部司は、単に蓄えるだけでなく「新たな価値を生み出す」部署でした。各地から納められた糸や布を材料に、当時最高峰の技を持った職人たちが、錦や綾といった至高の織物をはじめ、織染の技術を駆使して、高級織物を生産しました。 |
宮内省
この図は、宮内省の傘下組織を表したものです。宮内省は、天皇の衣食住から医療、宮殿の管理まで、宮廷運営の要となる役所でした。
| 名称 | 役割 |
| 大膳職 | 客人を招いた饗宴や、儀式用の大規模な食事の調理を担当。 |
| 内膳司 | 天皇が日常召し上がる食事の調理と、毒見などの安全管理を担当。 |
| 大炊寮 | 主食となる米や、煮炊きに使う穀物の管理・供給を担当。 |
| 造酒司 | 宮中で使用する酒や酢、お粥などの醸造を管理。 |
| 主水司 | 飲料水や製氷・氷室の管理、およびお供えする水の調達を担当。 |
| 木工寮 | 宮殿の造営や修理、木製の家具や道具の製作を行う建築・工芸の専門部署。 |
| 主殿寮 | 宮中の清掃、照明用の灯火、薪炭、お風呂などを管理。 |
| 掃部寮 | 宮中の畳の敷設や簾などを管理したり、儀式会場の設営、清掃を担当。 |
| 典薬寮 | 宮中の医療や薬の調達、および医師や針師などの育成を行う医療機関。 |
| 采女司 | 諸国から献上された采女(天皇の身の回りの世話をする女官)の管理・教育を担当。 |
豆知識
- 百人一首に登場する清少納言(62番)の『枕草子』には、削った氷に甘葛 をかけた、現代のかき氷の原型ともいえる「削り氷 」を食べる場面が登場しますが、夏の盛りまでその氷を溶かさずに守り抜き、宮中へ届けたのはこの主水司の役人たちでした。
- 2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に登場する田沼意次は、劇中で「主殿頭」と呼ばれていました。平安時代の「主殿頭」は、天皇の宮殿の管理や清掃を司る官職でしたが、江戸時代にはその実態はなくなり、家格に応じた一種の「名誉職」となっていました。実際の仕事内容とは関係がありませんが、かつての官職名が一種の権威として長く生き続けていたことがわかります。
馬寮
馬寮は、八省のどこにも属さず、太政官の直属する独立性の高い組織でした。
官馬の飼養・調習や馬具、諸国の牧を管理していました。
左馬寮と右馬寮というように左右に分かれていました。
豆知識
- 百人一首に登場する道因法師(82番)は馬寮 の左馬助を務めました。
兵庫寮
兵庫寮は、八省のどこにも属さず、太政官の直属する独立性の高い組織でした。
兵器や儀仗の維持管理を行いました。
官位相当表
下表は二官八省の官職と位階を表したものです。官職は位階(官人の序列を示す等級)に応じて任官される「官位相当 制」という仕組みが採用されていたため、官人にとって位階は重要でした。
| 位階 | 二官 | 八省 | ||||
| 位階 | 神祇官 | 太政官 | 中務省 |
式部省、治部省、 民部省、兵部省、 大蔵省、宮内省 |
刑部省 | |
| 正一位 | 太政大臣 | |||||
| 従一位 | ||||||
| 正二位 | 左大臣 右大臣 内大臣 |
|||||
| 従二位 | ||||||
| 正三位 | 大納言 | |||||
| 従三位 | 中納言 権中納言 |
|||||
| 正四位 | 上 | 卿 | ||||
| 正四位 | 下 | 参議(宰相) | 卿 | 卿 | ||
| 従四位 | 上 | 大弁 | ||||
| 従四位 | 下 | 伯 | ||||
| 正五位 | 上 | 左中弁 右中弁 |
大輔 | |||
| 正五位 | 下 | 左小弁 右小弁 |
大輔 | 大輔 大判事 |
||
| 従五位 | 上 | 少輔 | ||||
| 従五位 | 下 | 大副 | 少納言 | 侍従 大監物 |
少輔 | 少輔 |
| 正六位 | 上 | 少副 | 左弁大史 右弁大史 |
大内記 | ||
| 正六位 | 下 | 少祐 | 大丞 | 大丞 | 大丞 中判事 |
|
| 従六位 | 上 | 大祐 | 少丞 中監物 |
少丞 | 少丞 | |
| 従六位 | 下 | 少判事 | ||||
| 正七位 | 上 | 大外記 左弁少史 右弁少史 |
大録 中内記 |
大録 | 大録 | |
| 正七位 | 下 | 少監物 大主鈴 |
判事大属 | |||
| 従七位 | 上 | 少外記 | ||||
| 従七位 | 下 | 大典鑰 | 大解部 | |||
| 正八位 | 上 | 少録 少内記 少主鈴 |
少録 | 少録 | ||
| 正八位 | 下 | 大史 | 判事少属 中解部 |
|||
| 従八位 | 上 | 少史 | 少典鑰 | |||
| 従八位 | 下 | 少解部 | ||||
| 大初位 | 上 | |||||
| 大初位 | 下 | |||||
| 少初位 | 上 | |||||
| 少初位 | 下 | |||||
位階が五位以上を貴族、三位以上と参議(宰相)は公卿や上達部と呼ばれました。六位以下は貴族ではなく、地下人と呼ばれました。地下人は「じげにん」と読まれることもあります。
位階のピラミッド構造
次のピラミッドの図は位階(官人の序列を示す等級)を表したものです。位階は全部で30段階あり、上位の14段階まで(正一位~従五位下)が貴族とされていました。

蔭位の制 により、父祖の官位が一位から五位であれば、その子供は21歳以上で高い位を与えられ、キャリアをスタートできる特権が与えられていました。下表は、父親の位とその子、孫が任官される位を表したものです。一方で蔭位の制の恩恵に与れない人々は、大学を卒業したとしても正八位からスタートするのが一般的でした。しかも初めて位を与えられるのは25歳以上とされていました。
| 親の位 | 子供の位 | 孫の位 |
| 一位 | 従五位下 | 正六位上 |
| 二位・三位 | 六位~七位 | |
| 四位 | 七位~八位 | |
豆知識
- 2024年の大河ドラマ『光る君へ』で登場人物の多くが藤原氏だったのは、単なる偶然ではありません。「他氏排斥」によってライバルを消しただけでなく、この蔭位の制を巧みに利用して、一族が高いスタートラインから官界を独占し続けた結果であると考えられます。
治安と軍事
- 六衛府: 811年以降に定着した警備組織。宮中の門の守衛や天皇の護衛を担当します。
- 左右馬寮・兵庫寮: 軍事・儀式に欠かせない「馬」や「武器」を管理する現場です。これらは実用性と緊急性の観点から重要視され、特定の省には属さず、太政官直轄の組織として独立していました。
豆知識
- 百人一首に登場する道因法師(82番)は左馬寮の2等官である左馬助 でした。
六衛府
六衛府には、左右の近衛府、左右の衛門府、左右の兵衛府がありました。
警備範囲によってそれぞれの役割が分かれていました
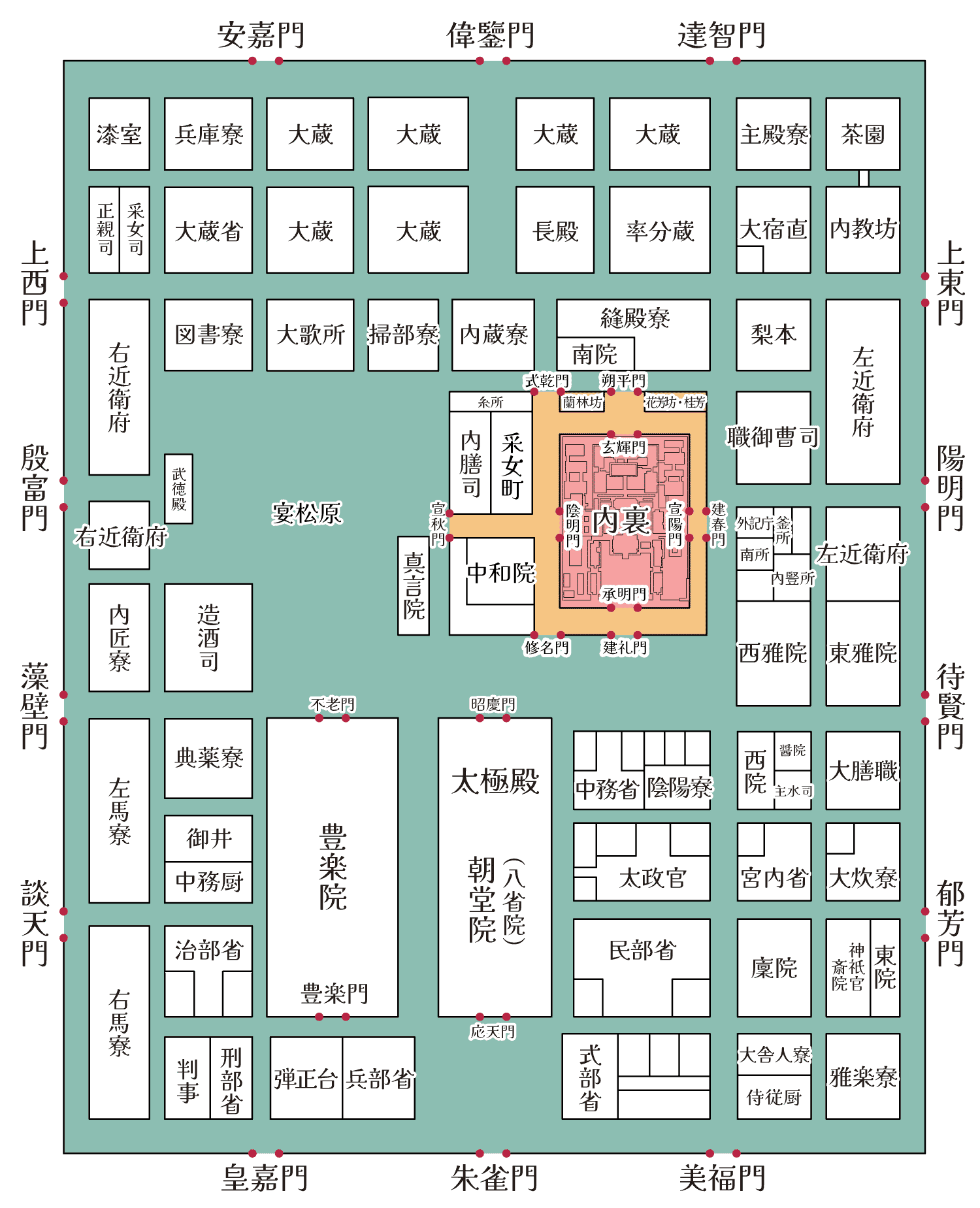
近衛府が警備
内裏の周囲
兵衛府が警備
大内裏の内側
衛門府が警備
近衛府
近衛府は奈良時代に設置され、その官職は律令の令制に規定がない令外官です。近衛府には、左近衛府 と右近衛府がありました。内裏内を警備したり、行幸(天皇のお出かけ)の際は行列に加わりました。
豆知識
- 百人一首に登場する右大将道綱母(53番 )は、息子の藤原道綱が中納言に昇進後に右近衛府の長官である大将を兼ねていたため、百人一首では「右大将道綱母」とされています。
衛門府
衛門府
は、大内裏内を警備し、行幸(天皇のお出かけ)の際は行列に加わりました。
衛門府には、左衛門府と右衛門府がありました。
豆知識
- 百人一首に登場する大中臣能宣(49番)の歌に登場する衛士は、衛門府に所属していました。
兵衛府
兵衛府 は、内裏周囲を警備し、行幸(天皇のお出かけ)や行啓(皇太子や皇后等のお出かけ)の際は行列に加わりました。兵衛府には左兵衛府と右兵衛府がありました。
豆知識
- 百人一首に登場する西行は、出家する前は左兵衛尉を務めていました。
弾正台
弾正台 は、独立した機関で官僚の不正を監視したり、京内の風俗の取り締まりを担当しました。検非違使が設置されると、弾正台の役割は検非違使に吸収され、弾正台は形骸化しました。
検非違使
検非違使は、嵯峨天皇の御代に京の治安維持のために設置された律令の令制に規定がない官職で「令外官 」です。後に刑部省、弾正台、京職などの仕事を吸収し、裁判も取り扱うようになりました。また、検非違使は衛門府の官人が任官されました。
検非違使のしもべには、元罪人で犯罪者を探したり、捕縛したり、拷問などを担当する放免 と呼ばれる人たちがいました。
遣唐使
遣唐使は飛鳥時代から平安時代にかけて、日本が唐に派遣された公式の使節団のことです。当時の航海技術では遭難のリスクが非常に高く、遣唐使は四艘の船に分かれて船団を組み、海を渡りました。どれか一隻でも無事に辿り着いて戻ってきてほしいという期待された命がけの国家プロジェクトでした。
豆知識
百人一首の歌人の中にもこの命がけの航海に運命を翻弄された人々がいます。
菅原道真(24番)は、唐に渡っていませんが、遣唐大使に任ぜられました。しかし、当時の唐の衰退と航海の危険性を指摘し、遣唐使の廃止を建議しました。これが認められ、894年に遣唐使は停止(後に廃止)。彼は、長きにわたる命がけの国家プロジェクトに終止符を打った人物となりました。
地方官制
中央から地方へ派遣される地方官は国司 と呼ばれました。任期は4年で現代における都道府県の知事のような立場ですが、行政、財政、司法、軍事を担い、大きな権限を持っていました。
国司
下表は国司の四等官制です。
| 階級 | 官職 | 職務 |
| 長官 一等官 |
守 | 祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司る長官 |
| 次官 二等官 |
介 | 長官の補佐 |
| 判官 三等官 |
大掾 > 少掾 | 公文書の審査など |
| 主典 四等官 |
目 | 公文書の作成・記録など |
各国の等級
各国は国力に応じて 大国、 上国、 中国、 下国に格付けされていました。

国司の位階と官職
国司の官職は、位階(官人の序列を示す等級)に応じて任官されました。位階と官職は国のランクにより、定められていました。
| 位階 | 大国 | 上国 | 中国 | 下国 | |
| 従五位 | 上 | 守 | |||
| 従五位 | 下 | 守 | |||
| 正六位 | 上 | ||||
| 正六位 | 下 | 介 | 守 | ||
| 従六位 | 上 | 介 | |||
| 従六位 | 下 | 守 | |||
| 正七位 | 上 | ||||
| 正七位 | 下 | 大掾 | |||
| 従七位 | 上 | 少掾 | 掾 | ||
| 従七位 | 下 | ||||
| 正八位 | 上 | 掾 | |||
| 正八位 | 下 | ||||
| 従八位 | 上 | 大目 | |||
| 従八位 | 下 | 少目 | 目 | ||
| 大初位 | 上 | ||||
| 大初位 | 下 | 目 | |||
| 少初位 | 上 | 目 | |||
| 少初位 | 下 | ||||
郡司
郡司は、現代の市区町村長のような存在で、地域の実情をよく知る地元の有力者が、無期限の任期で世襲的に任命されました。国司の下で、郡(現代における市町村のようなもの)の行政、徴税、軽微な刑罰執行などを担いました。
勘解由使
勘解由使 は、桓武天皇の御代に国司が不正をしないように監視するために設置されました。国司の交代時に引継ぎ文書を審査しました。律令の令制に規定がない「令外官」です。
大宰府
九州の筑前国に設置された役所で、外交や軍事が主任務でした。
豆知識
- 大宰府の四等官制は長官が大宰帥、次官を大宰大弐と言います。
- 百人一首 に登場する大弐三位(58番 )の名前は夫である高階成章が大宰大弐を務め、自身が従三位であったことに由来します。
京職
京職は京都の司法・警察・民政などを司った役所。京内を左右に分け、左京職・右京職に分かれます。京の東が左京、京の西が右京です。
豆知識
- 百人一首に登場する左京大夫道雅(63番)や左京大夫顕輔(79番)は、名前のとおり、左京職の長官である左京大夫を務めました。
武士
武士は、「侍ふ人」というのが語源とされており、本来は貴族の側でお仕えする人を意味していました。しかし、次第に国家規模で武力を使った解決が求められるようになると、朝廷は武士に位や官職を授け、こうして職能として武士が誕生しました。
| 呼称 | 定義 |
| 滝口の武士 | 蔵人所 の下で内裏の警護をした武士。滝口とは宮中の下水が地下に流れるところの美称で、滝口近くにある詰め所に宿直していました。内裏の警備は近衛府が担当していましたが、平城上皇と嵯峨天皇が争った薬子 の変があってから蔵蔵人所管轄で滝口の武士が警備するようになりました。 |
| 北面の武士 | 院の御所の北面に詰め、院中の警備をした武士で白河上皇のときに創設されました。 |
| 西面の武士 | 院の御所の西面に詰め、院中の警備をした武士で後鳥羽上皇のときに創設されましたが、承久の乱の後で廃止されました。 |
豆知識
- 百人一首に登場する西行(86番)は出家する前は北面の武士でした。
僧綱
全国の仏教の僧尼を管理するために国家から任命される官職で、次のように3階級ありました。
| 僧階 | 僧官 |
| 法印 一等官 |
大僧正 > 権大僧正 > 僧正 > 権僧正 |
| 法眼 二等官 |
大僧都 > 大僧都 > 権大僧都 > 権少僧都 |
| 法橋 三等官 |
大律師 > 律師 > 権律師 |
僧侶
| 呼称 | 定義 |
| 座主 | 天台宗を代表する僧侶。 |
| 入道 | 仏門に入るものの、剃髪のみで世俗の生活を続ける皇族や公卿のこと。 |
| 法師 | 法師とは、仏法によく通じ、人々を導く師となる者のこと。 |
| 講師 | 経典の講義をする僧。 |
| 山伏 | 山岳で修行する僧。 |
| 護持僧 | 天皇の身体護持のために祈祷を行う僧。 |
豆知識
百人一首にも、僧侶の歌人が何人かいます。
- 前大僧正慈円(95番)は比叡山延暦寺の天台座主を務めました。
- 法性寺入道前関白太政大臣(76番)は関白を辞任してから法性寺で出家しました。
- 前大僧正行尊(66番)は山伏修行をしながら歌を詠みました。
令外官
令外官は、律令の令制に規定がなく、実際の政治に合わせて新設された官職のことです。
下表は主な令外官の一覧です。
| 呼称 | 内容 |
| 摂政 | 866年、藤原良房は、清和天皇の幼少期に際し、皇族以外で初めて摂政に就任し、天皇に代わって政治の実権を掌握し、藤原氏による摂関政治の礎を築きました。 |
| 関白 | 光孝天皇の時代に藤原基経が実質的に天皇を補佐したことが関白の原型となり、宇多天皇の詔にある「案件は皆、太政大臣(基経)に『関り白 し』」という記述を根拠として、関白は正式な役職として確立しました。職務内容は、成年後の天皇を補佐し政務を統括することで、天皇への奏上内容の確認や意見具申、太政官からの意見の伝達などを行いました。 |
| 内覧 | 内覧は、897年に宇多天皇が醍醐天皇に譲位する際、藤原時平と菅原道真を新しい天皇の補佐に任じ、天皇への奏上文書を事前に閲覧させたことに始まります。 |
| 中納言 | 中納言は、705年に大納言の定員が4名→2名に減らされたことから、大納言の職務を補佐するために設置されました。太政官の四等官です。職務は大納言と同じで、政務の奏上(天皇への政務の報告、意見具申)、勅命の宣下(天皇の命令を臣下に伝える)でした。大納言のように大臣不在時に職務代行はできませんでした。 |
| 按察使 | 按察使は、714年に地方行政を監督する官職として設置されました。数か国の国守の内から1名を選任し、その管内における国司の行政の監察を行いました。794年に蝦夷 対策のために常設になりました。平安時代は、陸奥・出羽 だけを任地としました。やがて大納言・中納言の名目上の兼職となり、形骸化しました。 |
| 参議 | 参議は、705年に5人の官人を政治に参議させたのが始まりです。当時は官職名はありませんでしたが、731年に正式な官職になりました。平安時代では、四位以上の位階を持つ優秀な官人が8名任官され、政治の重要な決定に関わりました。公卿は、通常三位以上の位階を持つ者を指しますが、参議は四位であっても公卿に含まれます。 |
| 内大臣 | 669年、中臣鎌足が死の前日にそれまでの功績を称えられ、天智天皇から内臣という役職を授けられたのが始まりです。平安時代では、左大臣、右大臣に次ぐ地位になり、左右大臣が不在のときは政務や儀式を代行しました。 |
| 征夷大将軍 | 征夷大将軍は、709年に巨勢麻呂が蝦夷 を征討する朝廷軍の将軍として任命されたのが始まりです。797年に征夷大将軍の坂上田村麻呂が蝦夷のリーダーである阿弖流為 を降伏させました。坂上田村麻呂は坂上是則(百人一首 31番の歌人)の先祖にあたります。 |
| 勘解由使 | 勘解由使は、国司の不正に頭を悩ませていた桓武天皇の指示で797年頃に設置されました。国司が交代するとき、新任の国司は前任の国司に対して、事務引継ぎが問題なく行われたことを証明する解由状を発行します。勘解由使はその解由状を審査しました。現代の公認会計士や監査法人に相当する役割をしていました。 |
| 蔵人頭 | 平城上皇(兄)と嵯峨天皇(弟)が対立する中、薬子の変(平城上皇の変)の直前に嵯峨天皇が810年に天皇の機密事項を取り扱う「蔵人所 」を設置しました。蔵人頭はこの機関の長官です。この機関が作られた背景には、平城上皇の愛人関係にあった薬子の存在があります。彼女は、天皇の秘書官のような役割で、政治に影響力がある尚侍 という身分を与えられており、臣下への命令を下せる立場にありました。嵯峨天皇は薬子の影響力を排除するため、蔵人所 を設置したと考えられています。 |
| 検非違使 | 810年頃に平安京の治安維持を目的とした検非違使庁が設置されました。検非違使は、この機関に所属する官人です。平安京の治安維持は、それ以前は弾正台が担当していました。しかし、弾正台には逮捕権と裁判権がなく、都市化が進む平安京において治安維持が困難になっていました。そこで、弾正台よりも強力な権限を持つ検非違使庁が設置されることになったのです。検非違使庁の設立により、平安京の治安維持体制は強化され、犯罪の取り締まりや容疑者の逮捕、裁判などが迅速に行われるようになりました。 |
| 押領使・追捕使 | 9世紀末頃から、地方において武士が力をつけ始めました。彼らが紛争を起こした場合、本来は健児が鎮圧に当たるはずでしたが、武士の武力に対抗できず、朝廷は押領使や追捕使といった臨時の役職を設置しました。これらの役職は、武士の取り締まりや鎮圧を専門とし、健児よりも強力な権限を持っていました。 |
その他
| 呼称 | 定義 |
| 大宮人 | 宮廷につかえる人、殿上人。宮人ともいいます。大宮は皇居・神宮の尊敬語です。 |
| 君達/公達 | 公卿の子女、公卿の僧侶のことです。 |
| 殿上人 | 殿上人 は、天皇の住まいである清涼殿に昇ることを許された人のことを指します。一般的に五位以上の人は昇殿を許されました。また、六位の蔵人も天皇の秘書官であったため、昇殿を許されました。殿上人 は、雲上人や雲客 と呼ばれることもあります。 |
| 黄門 | 中納言の秦漢の職名。江戸時代の徳川光圀が黄門様と呼ばれていたことが有名ですが、『徒然草』の中で権中納言の藤原隆資という人物が「四条黄門」として登場しています。 |
| 皇太后宮大夫 | 皇太后宮職(皇太后宮に関する事務をつかさどった役所)の長官。藤原俊成は皇太后宮大夫を務めました。 |
| 公 | 太政大臣、左大臣、右大臣。 |
| 卿 | 大納言、中納言、参議(宰相)、三位以上の貴族。 |
| 公卿 | 公と卿を合わせたもの。公家と呼ばれることもあります。 |
| 貴 | 三位以上の人々。上級貴族。 |
| 通貴 | 四位、五位の人々。中級貴族。 |
| 曹司 | 宮中や貴族の邸内に部屋を与えられて仕える人 もともとの意味は 宮中に設けられた女官や官人の部屋のこと。 |
| 地下人 | 朝廷に仕える者で清涼殿殿上の殿上間に昇ることを許されない者のことです。 |
| 侍 | 上級・中級貴族に仕えていた正六位上の位階を持つ下級貴族。下級貴族の中に武士が混じっており、源頼朝や平清盛の先祖たちも元々は侍として上級貴族に仕えていたといわれており、平安時代中期頃から「侍」は武士を意味するようになったといわれています。「侍」の語源は「侍ふ」という動詞で、高貴な人の側近くで仕えるという意味を持ちます。 |
| 雑色 | 宮中で雑務を行う使用人。 |
| 僕 | 貴族に仕えて雑務を行う使用人。 |
| 市人 | 平安京の官設市場である「東市」、「西市」で商売を許可された男性。 |
| 市女 | 平安京の官設市場である「東市」、「西市」で商売を許可された女性。 |
| 販女 | 行商の女性。 |
| 馬借 | 馬を使う運送業者。 |
| 車貸し | 牛車を使う運送業者。 |
| 借上し | 金融業を行う下級僧侶。 |
| 儀同三司 | 太政大臣、左大臣、右大臣に准ずる「准大臣
」の別名。藤原伊周が准大臣に任命され、自らを儀同三司と称していたことがよく知られており、儀同三司と言えば藤原伊周を指すことが多いようです。 儀同三司母は伊周の母です。 |
| 蝦夷 | 東国地方に居住する朝廷に服属しない人々。 |
| 俘囚 | 朝廷に従属した蝦夷。 |
| 受領 | 現地赴任する国司のトップ。現地の支配を行う最高責任者のこと。 |
| 遙任 | 現地赴任せず、都にいて収入だけを得た国司。遙任国司とも呼ばれることもあります。 |
| 目代 | 遥任国司が自ら現地に赴く代わりに私的に派遣した代理人。 |
| 郡司 | 国司のもとにおかれ、地方行政の基礎単位となる郡を治める者。在地の豪族が任命され、実際の徴税業務を行いました。 |
| 田堵 | 名田(課税対象となる土地)の経営(耕作・納税)を請け負う有力農民のこと。その中でもさらに有力な田堵で、大規模な土地を経営した者は、大名田堵 と呼ばれます。 |
| 下人 | 田堵に隷属的に扱われた農民のこと。 |
| 開発領主 | 墾田永年私財法 に基づき、開墾されていない土地を私力で開発し、その土地の所有者となった者のこと。 |
| 荘官 | 開発領主は、開発した土地を国司からの干渉を防ぐため、貴族や寺社などの有力者に寄進しました。寄進した土地は荘園と呼ばれ、開発領主は、荘園を管理する荘官という立場になりました。荘官は、有力者に寄進した見返りに寄進先から不輸の権(税金を納めなくてよい権利)、不入の権(国司が荘園に立ち入って調査することを拒否できる権利)を得ました。 |
| 朝臣 | 五位以上の位階を持つ者につける敬称。最初は皇族から分家した貴族に付けられていました。三位以上は姓の下、四位、五位は名の下に付けたといわれていますが、諸説あります。 |
| 侍従 | 高貴な立場の人物に付き従い、身の回りの世話などをする者のこと。 |
| 太夫 | 五位以上の位階を持つ者 読み方は「たゆう」または「たいふ」 |
| 頭中将 | 蔵人頭と近衛中将(近衛府の次官)を兼任した者の通称 |
| 頭弁 | 蔵人頭と弁官(少弁、中弁、大弁)を兼任した者の通称 |
| 明法博士 | 大学寮の明法道(律・令・格・式など法律学を学ぶ学科)の教官。 |
| 舎人 | 皇族や貴族の身辺に仕えて、警備や雑用に携わる下級官人 |
| 関守 | 関所の番人 源兼昌の歌に「須磨の関守」が登場します。 |
| 防人 | 筑紫・壱岐・対馬など北九州を防衛した兵士 |
| 散位 | 位階はあるが官職のない者 |
| 北の方 | 公卿など身分の高い人の正妻の敬称 |
番外編:位階を与えられた動物
| 呼称 | 定義 |
| 五位鷺 | 醍醐天皇が神泉苑に御幸になったとき召使い捕らえるよう命じられました。召使いが近づくと鷺は飛び立とうとしましたが、「帝の勅命であるぞ」と呼びかけられると鷺はひれ伏しました。天皇は神妙な鳥だと感嘆され、正五位を授けたといわれています。 |
| 命婦の御許 | 命婦とは五位以上の位階を持つ女官、また五位以上の位階を持つ官人の妻のこと。一条天皇の飼い猫は官位を授けられ、「命婦の御許」と呼ばれました。「御許」は高貴な女性への敬称です。 |
補足:四等官について
どの役所にも基本的に「かみ・すけ・じょう・さかん」という4つの階級の責任者が置かれました。現代の組織に例えると「社長・部長・課長・係長」のような構成ですが、当時の役職名の漢字は、所属する役所(省、職、寮、司など)によって使い分けられていました。下表のように役所ごとに漢字は異なりますが、その職務内容は共通です。
| 種類 | 長官 | 次官 | 判官 | 主典 |
| 省 神祇官 |
伯 | 大副 > 少副 | 大祐 > 少佑 | 大史 > 少史 |
| 省 (式部省・民部省など) |
卿 | 大輔 > 少輔 | 大丞 > 少丞 | 大録 > 少録 |
| 職 (中宮職・京職など) |
大夫 | 亮 | 大進 > 少進 | 大属 > 少属 |
| 寮 (図書寮・雅楽寮など) |
頭 | 助 | 大允 > 少允 | 大属 > 少属 |
| 近衛府 | 大将 | 中将 > 少将 | 将監 | 将曹 |
| 衛門府・兵衛府 | 督 | 佐 | 大尉 > 少尉 | 大志 > 少志 |
| 検非違使 | 別当 | 佐 | 大尉 > 少尉 | 大志 > 少志 |
| 大宰府 | 帥 > 権帥 | 大弐 > 少弐 |
大監 > 少監 |
大典 > 少典 |
| 国司 | 守 | 介 | 掾 | 目 |