平安王朝の女性作家たち
後宮に仕える女房
平安時代、紫式部をはじめとする女性作家たちの多くは、天皇の后に仕える「女房」として活躍していました。この「女房」とは、妻という意味ではなく、住み込みで高貴な人の世話をする女性のことです。彼女たちは、自分専用の「房(=部屋)」を持ち、高い教養と礼儀を求められる憧れの職業でした。宮廷で貴族文化に触れながら、彼女たちは文学を執筆する機会を得ていました。
一条天皇と「一帝二后」
一条天皇は藤原道隆の娘である定子を中宮(最高位の后)として迎え、深く愛していました。しかし、藤原道長は定子を皇后とし、さらに自分の娘である彰子を中宮として即位させました。皇后は中宮の別称で同じ意味なのですが、道長は異なる敬称を使い分けることで、最高位の后が二人存在する一帝二后 の状態を強引に作り上げました。
藤原氏は、自分の娘を天皇に嫁がせ、その娘に天皇の子供を産ませ、外戚(母方の親戚)になることで政治の主導権を握る手法を取っていました。道長にとって娘である彰子を強引に后にすることは政治的な戦略だったと考えらます。
彰子の女房に選ばれた紫式部
彰子は一条天皇の子をもうけることが期待されていましたが、一条天皇は定子を深く愛していたため、彰子にはあまり関心を寄せていませんでした。定子には教養豊かな清少納言が仕えており、その知性に一条天皇は惹かれていました。そこで道長は、一条天皇の注意を彰子に向けるため、当時人気を博していた『源氏物語』の著者である紫式部を彰子の女房として迎え入れ、一条天皇が彰子のもとを訪れるように計画したと伝えられています。
清少納言に対する紫式部の評価
紫式部と清少納言は同時代の作家でしたが、宮仕えをしていた時期は少し異なります。インターネットでは2人は仲が悪かったという情報が散見されますが、実際は清少納言が宮仕えを辞めた6年後に、紫式部が宮仕えを始めており、少なくとも2人の仲は表立って悪かったわけではないようです。ただし『紫式部日記』の中で、紫式部は清少納言について次のように記しています。
原文
清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書きちらしてはべるほども、よく見れば、まだいとたらぬこと多かり。
現代語訳
清少納言は得意顔が甚だしい人でした。あれほどまでに利口ぶって漢字を大っぴらに書いているが、よく見るとまだまだ足りない点が多くあります。
平安時代では、女性の奥ゆかしさが美徳とされていました。紫式部も、他の女性たちに嫉妬されないよう、漢字が書けないふりをしていたといわれています。そのため、積極的に知識を披露していた清少納言は、当時の感覚では才能をひけらかしているように見えたのかもしれません。
平安文学の双璧
清少納言と紫式部
2人の仲はさておき、清少納言と紫式部は平安時代の文学界における傑出した作家でした。
清少納言は、和歌の名手である清原元輔を父に持ち、その影響で幼少期から豊かな文学教育を受けました。彼女は五感に優れ、美的感覚も非常に高かったため、その感性を『枕草子』で見事に表現しました。
一方、紫式部は漢文学に秀でた父を持ち、彼女もまた子供の頃から父親の影響で文学に親しんでいました。物語好きで鋭い観察眼を持つ紫式部は、その才能を『源氏物語』で余すところなく発揮しました。
女性作家たちの系図
定子には清少納言が仕え、彰子には紫式部を含む6名の女性作家が仕えていました。大弐三位は紫式部の娘で、小式部内侍は和泉式部の娘です。これにより、親子二代にわたって彰子に仕えました。教養の高い女性作家たちが集まり、宮廷文化に触れながら文学を執筆し、後世に残る随筆や小説、日記文学が誕生しました。
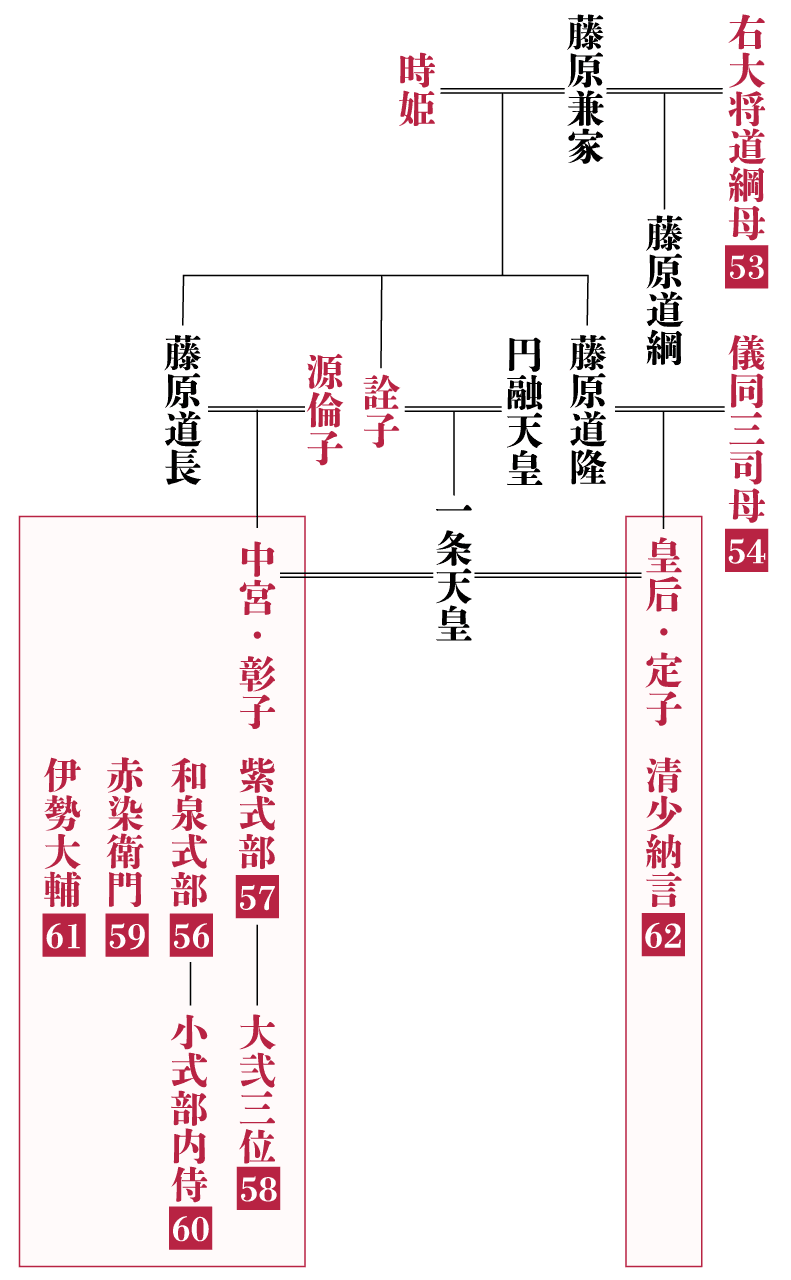
■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。
公卿の第二夫人になった作家
右大将道綱母
『蜻蛉日記』を執筆した右大将道綱母は、公卿である藤原兼家の2番目の妻でした。『蜻蛉日記』には執筆の動機が次のように書かれてあります。
原文
人にもあらぬ身の上まで書き日記して、めづらしきさまにもありなむ。天下の人の品高きやと問はむためしにもせよかし
現代語訳
人並でない私の身の上を書き日記にしたら珍しい作品になるでしょう。身分高き男性と結婚する女性の生活がいかなるものかを知る例にしてほしい。
道綱母は、夫である兼家との出会いから関係が途絶えるまでの自らの経験を三人称で描きました。浮気性の夫に対する嫉妬や悩みが率直に吐露される一方で、権力者である夫と対等に渡り合いながら逆境を生き抜いた誇り高い女性の姿が垣間見える、物語風の日記に仕上がっています。
平安時代の通い婚
平安時代の第2夫人は、「通い婚」と呼ばれる婚姻形態をとっていました。これは、夫が気が向いたときに夜に通ってくるというものです。道綱母は、裕福な生活を送っていただけでなく、夫が訪れない間に十分な時間があったため、自由に執筆できる環境を持っていたと考えられます。ただし、気まぐれにしか訪れることがない夫を持つストレスは大きく、その状況は『蜻蛉日記』からよく伝わってきます。